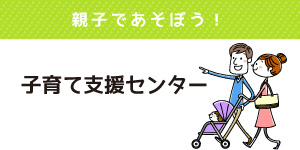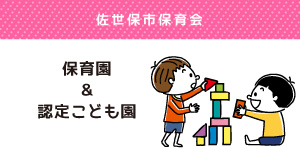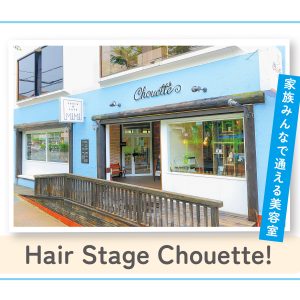今年度も残り3ヶ月となりました。1年を振り返ったり、来年度に向けてあれこれと考える時期ですね。ママパパ編集部にも子育てに関するいろいろな質問が寄せられます。そこで、今回は、20年以上の子育て支援の経験を持つ認定専門公認心理師・臨床心理士である吉田直樹先生に答えてもらいます。
親がどのような子育てをするかで、子どもの性格が決まるというのは本当でしょうか?もしそうであれば、どのようなところに気を付ける必要がありますか?
心理学では、「性格」を「パーソナリティ」と呼ぶことが一般的で、人間の行動や判断のもとになる考え方や傾向のことを指します。具体的には、2つの意味があり、一つは、人間が生まれつき備えている性格や気質、もう一つが家族や生活環境、周囲との人間関係など、子どもから大人になる成長の過程で徐々に形成されるものに分かれます。したがって、子どもが生まれ持った性格は変えられませんが、成長過程で形成される性格には親の養育態度が影響するのです。 幼児期の子どもの性格形成と親の養育態度の研究によると、親が支配的だと、従順だが消極的だったり依存的な傾向が見られます。親がかまいすぎると、子どもが幼児的だったり神経質、受動的になります。また、親が甘やかしたり、子どもの言いなりになったり、無視したりすると、子どもが反抗的、攻撃的、乱暴、情緒不安定になるので注意が必要です。
病院などで、子どもが静かにできないと、スマホやタブレットで動画を見せたり、アプリで遊ばせてしまいます。悪いとはわかっているのですが・・・
子育て中は、親も仕事や家事で忙しいので、子どもの機嫌が悪いと、ついスマホやタブレットに頼りたくなりますよね。では、どのようなところに気を付けるといいのでしょうか? まず、子どもは、「スマホやタブレットで遊びたい」という自分の欲求をコントロールする自制心が未熟であることを意識しましょう。幼児期や小学校低学年までは、約束してもなかなか守ることができないのはこれが原因です。したがって、親が使い方を管理することが必要なのです。 次に、スマホやタブレットの使い過ぎると脳が疲れて、子どもも大人も認知機能が低下することが研究で明らかにされています。記憶を例にすると、私たちにはワーキングメモリという短い時間に心の中で情報を保持し、同時に処理する能力が備わっています。これは、会話や読み書き、計算などの基礎となり、日常生活や学習を支える重要な能力です。スマホを使い過ぎていると、常にワーキングメモリーに新しい情報や刺激が入ってくるので脳が休む時間がありません。そのため、記憶を整理する時間もなくなり、しだいに脳が疲れて、もの忘れや記憶力の低下、思考力や集中力の減退を引き起こすのです。人間は、ぼんやりすることで、情報を整理して記憶を定着させますので、親子でボーっと過ごす時間も大切にするといいですね。
習いごとを始めたのはいいのですが、やめたいと言い出しました。どうするのがいいのでしょうか?
ピアノを習った人が、全員ピアニストになるわけではありません。サッカーがいくら得意でも、プロとして通用するのは、ほんの一握りの選手です。では、何のために習いごとをさせるのでしょうか?家庭ではなかなかできない習いごとでの体験により、知識や技術の習得を通して認知能力を伸ばすとともに、目に見えない子どものこころの力を育むことが大きな目的です。具体的には、「できた」という経験により自信をつけたり、自らの興味により継続する力を身に着けることなどがあげられます。 まず、「どうしてやめたいのか?」理由を確かめましょう。しかし、子どもに聞いてもわからないこともあるので、親が習いごとへ一緒に行って観察したり、指導者に相談することも重要になります。そして、改善したり、時間が必要な場合には様子を見ることも必要です。子どもにとっては、今後、何かをやめることのモデルになるので、簡単に辞めさせるのではなくステップを踏むことを大切にしましょう。
習い事で「非認知能力を伸ばすことが大切」と言われたのですが、あまりピンときませんでした。どのようなに理解したらいいのでしょうか?
最近、幼児教育、保育の分野で「非認知能力」ということばがよく使われているようです。ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマンの研究で「非認知能力」あるいは「非認知スキル」という言葉が用いられ世界中に広がりました。「非認知能力」は「IQ(知能指数)では表せないこころの力」とされていますが、学術的な定義は難しく、私たち心理学の専門家の間でもさまざまな意見があります。OECD(経済協力開発機構)の「家庭、学校、地域社会における社会情動的スキルの育成」によるとIQを意味する認知能力と対比して、非認知能力を「社会情動的スキル」と定義しています。「社会情動的スキル」とは、目標の達成、他者との協働、情動の制御に関わるスキルで、具体的には「忍耐力」や「思いやり」、「自尊心」などが含まれます。このように、認知能力と非認知能力は、車に例えると両輪のようなものなので、どちらを伸ばすのではなく、バランスよく育むことが重要なのです。
他の記事
-
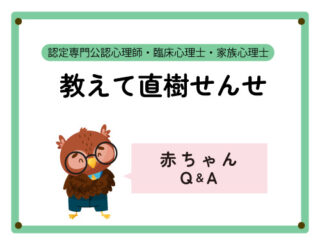
-
「赤ちゃんQ&A」(WEB版2025年3月・4月号掲載)
待ちに待った春になりましたね。あたたかくなってきたので「赤ちゃんと公園デビューするかな?」「子育て支援センターなどに遊びにいってみようかな?」「家では活発すぎて持て余し気味なのでお出かけしないと!」 ...
-

-
「入学までに親が気を付けるポイント」(WEB版2025年1月・2月号掲載)
入学を前に「私が小学校に入学するようで落ち着きません」「友達やお勉強、給食のことなど、心配が止まりません」などなどいろいろなことが不安になるようです。そこで、今回は、スクールカウンセラーとしての長い経 ...
-
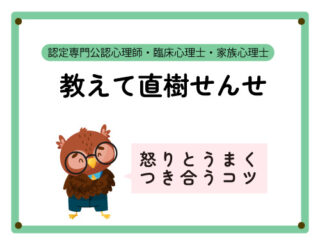
-
「怒りとうまくつき合うコツ」について(WEB版2025年1月・2月号掲載)
家事や子育てに追われていると、ついついイライラして子どもに当たってしまうことってありますね。ママパパ編集部にも「怒りたくないのに怒ってしまいました」「キレるのは悪いことだってわかっているのに・・・」と ...