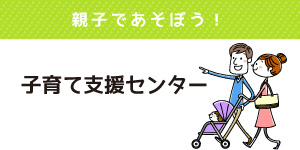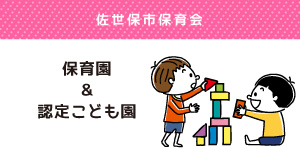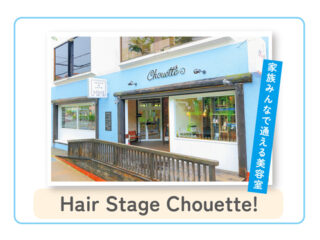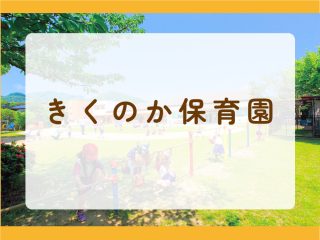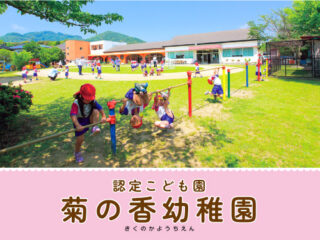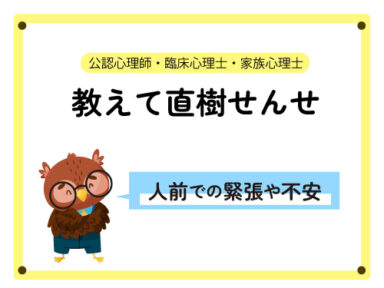
入学や入園のシーズンです。子どもたちにとっては、ウキウキワクワクですが、ママにとってはママ友作りや新しい担任の先生との関係などなど、右往左往してしまうようなストレスフルなことが多くなる時期ですね?そこで、今回は「人前での緊張や不安」について、医療機関で心身症を専門としている、公認心理師・臨床心理士の吉田直樹先生に、読者の皆さんの質問に答えてもらいました。

程度の差はありますが「自分が他人にどう見られているか」気になることはありますね。「誰にでもある日常生活の中の不安」です。今までは「性格の問題」として切り捨てられ、一人で苦痛を抱え込む方も多かったようですが、最近は改善できるこころの問題としてとらえられるようになってきています。子どもの場合は、早期に対応することが大切です。

緊張すると身体に現れるこころの反応かもしれません。動悸や息苦しさ、めまい、顔のこわばり、吐き気、口の渇きなどを訴える人もいます。医療機関を受診しても身体の異常はないことがほとんどで、不安や恐怖といった心理的なことが原因で起こります。「また汗をかくかもしれない」「震えたらどうしよう」と身体の反応を意識すると、さらに緊張が高まり悪循環になることも多いようです。日常生活に支障がある場合は、早期に心理の専門家に相談されるといいでしょう。

TVやインターネットなどでリラックス法がたくさん紹介されていますね。最近は、「マインドフルネス」というキーワードでも検索できます。ただ、不安や緊張のレベルが高いとリラクセーショントレーニングの効果を実感することが難しいようです。まず、どのような場面で緊張したり、不安を感じるのかチェックします。次に、不安や緊張するときに、自分に起こるこころや身体の反応を観察してください。これは、心理学でモニタリングというプロセスで、自分自身に気づく練習です。そして、不安や緊張が一番弱い場面をイメージして、リラックスする練習からスタートします。不安や緊張のレベル、身体やこころの反応は、おとなはもちろん子どもにも認識できないこともあるので、メンタルトレーニングを受けて、自分に合ったリラクセーション法を身に着けるのもお勧めです。

人間関係やコミュニケーションの悩みは「相談しても仕方がない」と思い込んでいる人がほとんどです。科学的に効果が証明されたカウンセリングなど有効な方法もありますから、じっと耐え続けるのではなく、改善へ半歩でも踏み出すことを大切にしてください。決して「気持ちを強く持つ」「やればできる」など精神論で解決するような問題ではありません。考え方や捉え方を変える認知行動療法や自分の考えや気持ちを上手に伝えるアサーション・トレーニングが代表的なカウンセリングで、子ども専用のプログラムもありますよ。

一般的に、視線への不安や恐怖を感じるのは、社交不安障害の基本的な症状の一つだと言われています。10人に1人から2人は似たような悩みを持っているとされ、決して珍しいことではありません。うつ病やパニック障害、依存症などを併発するリスクもあります。日常生活に支障が出ているようであれば、臨床心理士・公認心理師に相談されことをお勧めします。
その他の記事
-
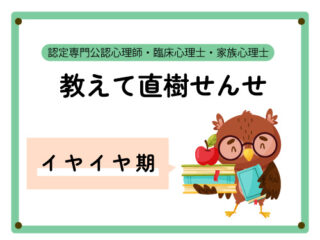
-
「イヤイヤ期」について(2025年11月・12月号掲載)
子育てをしていると子どものいろいろな問題に遭遇します。「発達の特性」や「コミュニケーション能力」「がまんする力(セルフコントロール)」「しつけ」「社会のルールやマナー」「お友達との関わり」など、気にな ...
-
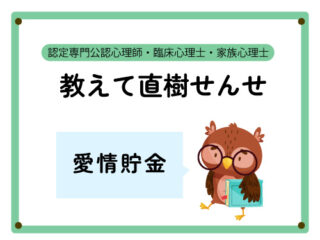
-
「愛情貯金」について(2025年9月・10月号掲載)
ママ友との関係や親子関係などなど、人間関係の悩みはつきませんね。でもやっぱり避けられないのが「夫婦関係」です。「夏休みに夫婦で過ごす時間が増えてケンカになりました」「家族旅行に行ったのに私たち夫婦がギ ...
-
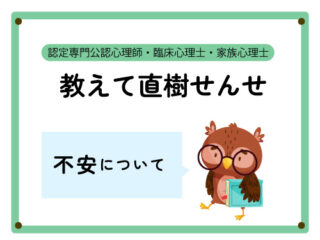
-
「不安症」について(2025年7月・8月号掲載)
今年度もスタートして3ヶ月が過ぎました。子どもはもちろんママやパパの身体やこころにも疲れが出るころですね。「新しいママ友と話して緊張した!」「初めての参観日があり、子どものことが心配でドキドキです」「 ...